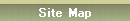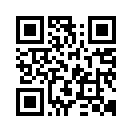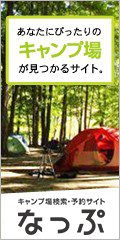『へたれ山ヤの漢気日記』 に訪問ありがとうございます。
『へたれ山ヤの漢気日記』 に訪問ありがとうございます。
 登山の道具,ウェア,グッズ,書籍,映像などのインプレと山行記録をメインに書いています。
登山の道具,ウェア,グッズ,書籍,映像などのインプレと山行記録をメインに書いています。 登山に関連するアウトドアやキャンプの道具&グッズ・書籍と幕営記録も書いています。
登山に関連するアウトドアやキャンプの道具&グッズ・書籍と幕営記録も書いています。 最近はマウンテンバイク『ROCKRIDER5.2』のポタリングやパーツレビューも書いています。
最近はマウンテンバイク『ROCKRIDER5.2』のポタリングやパーツレビューも書いています。 記事は全てカテゴリー別になっていますので宜しければ左サイドメニューの項目も参照下さい。
記事は全てカテゴリー別になっていますので宜しければ左サイドメニューの項目も参照下さい。 上部ナビボタンを使用すると当サイトの記事一覧や画像一覧等の検索が容易に出来ます。
上部ナビボタンを使用すると当サイトの記事一覧や画像一覧等の検索が容易に出来ます。 追記もしくは訂正の記述が特にない場合は記事投稿時点での価格及び情報になります。
追記もしくは訂正の記述が特にない場合は記事投稿時点での価格及び情報になります。 記事を参考に購入や加工等をされる場合は自己責任でお願いします(一切責任を負いません)
記事を参考に購入や加工等をされる場合は自己責任でお願いします(一切責任を負いません) 「IE」「Chrome」以外のブラウザ及びスマホ・携帯等では正常に表示されない場合があります。
「IE」「Chrome」以外のブラウザ及びスマホ・携帯等では正常に表示されない場合があります。 HOME >
SITE MAP >
参考書
>>
参考書№286 50歳からはじめるハイキングの教科書
HOME >
SITE MAP >
参考書
>>
参考書№286 50歳からはじめるハイキングの教科書記事投稿日:2012年10月25日
デフォルメされたイラストと大きめのQ数で年配者でも読みやすい。
道具や様々な知識がまんべんなく解説されている(下記目次参照)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【目次】
■PART1 ハイキングを楽しむ(計画と準備編)
初めて出かけるハイキング
・アウトドアの楽しみ方の一つにハイキングがある
仲間を作って楽しく遊ぶ
・ハイキング仲間はいろいろな楽しみ方を創り出す
行動計画を立てる
・計画には8つの基本原則がある
・山の高さと気温の関係を知っておくことが大事
所要時間の基準を確認する
・歩きと休憩のポイントは、同行者全体のリズム
・ハイキングの行動計画に変化をつける
50歳代からは無理は禁物
・身体をいたわり、楽しいハイキング
地形図を活用しよう
・地形図という地図の一種
・等高線を読む
やはりコンパスは持っていたほうがいい
・なぜ山でコンパスが必要なのか
・「磁針偏差」っていったい何?
使いこなしてこそコンパス(実践)
・現在地を確認する
ハイキングの天気の知識
・高気圧と低気圧
・天気図の見かたに慣れる
・山の高度と山での風について
■PART2 ハイキングの道具をそろえよう
高機能でファッション性の高いウェア
・シャツは保温と通気性
・目立つ色はファッション性ばかりではない
野山ハイキングでのウェアは臨機応変に
・素材を選び、寒暖に合わせて重ねて着る
ウェアやトレッキングパンツの機能と素材
・丈夫さと運動性を併せ持つ
・高機能なアンダーウェアは命を守る
雨具はトレッキングの重要な道具
・雨に降られても楽しくなるような雨具にする
・「防水性」と「透湿性」がポイント
・セパレートタイプが便利で機能的
ザックの選び方
・行程や日数を考えてザックの容量を決める
ザックに実際にパッキング(収納)する
・収納物を使うときのことを考えて
・機能を知った上でザックを選ぶ
トレッキングシューズの選び方
・目的と靴の種類を知っておく
靴を買うときは必ず試し履きをする
・山用品専門店の靴コーナーでいろいろ履き比べる
使うと便利な野山ハイキングの道具
・装備をしっかりすればハイキングがもっと楽しくなる
・よさそうなものは積極的に使ってみよう
ハイキングに持っていくと楽しい道具
・最近の山用品は究極のハイテク・グッズ
・ハイキングで必ず重宝する食料
■PART3 楽しく安全なハイキング(行動編)
ハイキングの前に、まずストレッチ
・呼吸を止めずに、筋肉を温める
ハイキングの基本・ラクな歩き方
・足の裏全体で、土の上を踏み進んでいくイメージ
・靴ひもは状況に応じて調整する
歩行ペースと休憩時間のとり方
・歩行は「30に10」のペースを意識
上りと下りの歩き方・平地、上りはリーダーが最後尾から
・野山のハイキングは下りが肝心
水分・塩分・糖分・を適度にとる
・「水を飲むとバテる」は迷信
・少量の「塩」は効果的
ハイキングのときのトイレは
・さて、どこでどうやって用を足そうか
・「キジ撃ち」をするとき
ヤブと森の中の歩き方
・「ヤブこぎ」は平泳ぎの要領で
・ヤブで迷ったときは
渡渉、丸木橋、吊り橋を行く
・川の安全な渡り方
・ふくらはぎの中ほどまでがやめる目安
・丸木橋や吊り橋を渡る
岩場、クサリ場、ガレ場を超える
・安全に岩場を超える方法
・クサリ場、ガレ場を超える方法
コースルートとマーキング
・指導標とマーキング
・道をまちがえたときは引き返す
野山のハイキングで楽しむ道草
・歩いているばかりではつまらない
・小腹がすいていたら軽くエネルギーの補給
野山ハイキングの昼ごはん
・にぎり飯は基本だが、もうひと工夫
山小屋(山荘)に泊まる
・寝具・食事つきの山小屋
無人の山小屋に泊まる
・寝る場所を譲りあうルール
■PART4 ハイキングの楽しみ方いろいろ
ハイキングで四季を楽しむ
・春の桜、新緑の森を歩く
・紅葉の森や林を歩く
ハイキングで見よう、野山の樹木
・樹木の自然観察は楽しい
山菜を見つける
・山菜採りはルールとマナーを守って
山菜のおいしい食べ方
・アク抜きをしてから食べる
・食べ方のアラカルト
・春の七草がりをしよう
キノコ狩りを楽しむハイキング
・キノコ狩りのルール
食べられる木の実
・よく見れば食べられるものも多い
野鳥観察、鳥の居場所を探そう
・耳をすまし、しっかりと森を見る
野山のハイキングで見られる滝
・滝はハイキング途中のオアシス
野生動物のフィールドサイン(痕跡)を探す
・足跡やフンで動物を推定する
野山ハイキングのあとは温泉宿などで楽しむ
・ハイキングと温泉の旅を組み合わせる
天候などの要因で計画の変更も
・荒天などによるコース変更の予定も考えておく
■PART5 ハイキングで起こるさまざまな事に備える
ハイキングで道に迷った場合
・鉄則① 今、来た道を戻る
・鉄則② その場にとどまる
・鉄則③ 沢(谷)の方には下らない
・迷ってしまった仲間(同行者)を探す
ビバーク(野宿)するときには
・決断を早くしたら、場所の確保
不幸にして遭難してしまったら
・救難を待つ方法
雨、霧で視界不良のとき
・リーダーの判断と全員の協力
山の災害から身を守る
・怖い!がけ崩れ、土砂崩れ
「かみなり」が近づいてきたときの対処法
・かみなりの特徴をよく知る
熱中症に備える
・適度な塩分をとることが大切
ケガをしたときの止血法
・出血を見て止血をする
・止血法を選ぶ
ねんざ、打ち身、骨折などをしたとき
・ハイキングで多いのは「ねんざ」
ハチ、毒虫、毒ヘビなどにやられたとき
・応急処置を施したら、早めに病院へ
さる、クマの対策
・里山でも遭遇してしまうサルやクマ
人工呼吸と心肺蘇生法
・呼吸が止まっていたら人工呼吸
・心肺蘇生を行う
道具や様々な知識がまんべんなく解説されている(下記目次参照)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
楽天ブックスはこちら↓
|
【目次】
■PART1 ハイキングを楽しむ(計画と準備編)
初めて出かけるハイキング
・アウトドアの楽しみ方の一つにハイキングがある
仲間を作って楽しく遊ぶ
・ハイキング仲間はいろいろな楽しみ方を創り出す
行動計画を立てる
・計画には8つの基本原則がある
・山の高さと気温の関係を知っておくことが大事
所要時間の基準を確認する
・歩きと休憩のポイントは、同行者全体のリズム
・ハイキングの行動計画に変化をつける
50歳代からは無理は禁物
・身体をいたわり、楽しいハイキング
地形図を活用しよう
・地形図という地図の一種
・等高線を読む
やはりコンパスは持っていたほうがいい
・なぜ山でコンパスが必要なのか
・「磁針偏差」っていったい何?
使いこなしてこそコンパス(実践)
・現在地を確認する
ハイキングの天気の知識
・高気圧と低気圧
・天気図の見かたに慣れる
・山の高度と山での風について
■PART2 ハイキングの道具をそろえよう
高機能でファッション性の高いウェア
・シャツは保温と通気性
・目立つ色はファッション性ばかりではない
野山ハイキングでのウェアは臨機応変に
・素材を選び、寒暖に合わせて重ねて着る
ウェアやトレッキングパンツの機能と素材
・丈夫さと運動性を併せ持つ
・高機能なアンダーウェアは命を守る
雨具はトレッキングの重要な道具
・雨に降られても楽しくなるような雨具にする
・「防水性」と「透湿性」がポイント
・セパレートタイプが便利で機能的
ザックの選び方
・行程や日数を考えてザックの容量を決める
ザックに実際にパッキング(収納)する
・収納物を使うときのことを考えて
・機能を知った上でザックを選ぶ
トレッキングシューズの選び方
・目的と靴の種類を知っておく
靴を買うときは必ず試し履きをする
・山用品専門店の靴コーナーでいろいろ履き比べる
使うと便利な野山ハイキングの道具
・装備をしっかりすればハイキングがもっと楽しくなる
・よさそうなものは積極的に使ってみよう
ハイキングに持っていくと楽しい道具
・最近の山用品は究極のハイテク・グッズ
・ハイキングで必ず重宝する食料
■PART3 楽しく安全なハイキング(行動編)
ハイキングの前に、まずストレッチ
・呼吸を止めずに、筋肉を温める
ハイキングの基本・ラクな歩き方
・足の裏全体で、土の上を踏み進んでいくイメージ
・靴ひもは状況に応じて調整する
歩行ペースと休憩時間のとり方
・歩行は「30に10」のペースを意識
上りと下りの歩き方・平地、上りはリーダーが最後尾から
・野山のハイキングは下りが肝心
水分・塩分・糖分・を適度にとる
・「水を飲むとバテる」は迷信
・少量の「塩」は効果的
ハイキングのときのトイレは
・さて、どこでどうやって用を足そうか
・「キジ撃ち」をするとき
ヤブと森の中の歩き方
・「ヤブこぎ」は平泳ぎの要領で
・ヤブで迷ったときは
渡渉、丸木橋、吊り橋を行く
・川の安全な渡り方
・ふくらはぎの中ほどまでがやめる目安
・丸木橋や吊り橋を渡る
岩場、クサリ場、ガレ場を超える
・安全に岩場を超える方法
・クサリ場、ガレ場を超える方法
コースルートとマーキング
・指導標とマーキング
・道をまちがえたときは引き返す
野山のハイキングで楽しむ道草
・歩いているばかりではつまらない
・小腹がすいていたら軽くエネルギーの補給
野山ハイキングの昼ごはん
・にぎり飯は基本だが、もうひと工夫
山小屋(山荘)に泊まる
・寝具・食事つきの山小屋
無人の山小屋に泊まる
・寝る場所を譲りあうルール
■PART4 ハイキングの楽しみ方いろいろ
ハイキングで四季を楽しむ
・春の桜、新緑の森を歩く
・紅葉の森や林を歩く
ハイキングで見よう、野山の樹木
・樹木の自然観察は楽しい
山菜を見つける
・山菜採りはルールとマナーを守って
山菜のおいしい食べ方
・アク抜きをしてから食べる
・食べ方のアラカルト
・春の七草がりをしよう
キノコ狩りを楽しむハイキング
・キノコ狩りのルール
食べられる木の実
・よく見れば食べられるものも多い
野鳥観察、鳥の居場所を探そう
・耳をすまし、しっかりと森を見る
野山のハイキングで見られる滝
・滝はハイキング途中のオアシス
野生動物のフィールドサイン(痕跡)を探す
・足跡やフンで動物を推定する
野山ハイキングのあとは温泉宿などで楽しむ
・ハイキングと温泉の旅を組み合わせる
天候などの要因で計画の変更も
・荒天などによるコース変更の予定も考えておく
■PART5 ハイキングで起こるさまざまな事に備える
ハイキングで道に迷った場合
・鉄則① 今、来た道を戻る
・鉄則② その場にとどまる
・鉄則③ 沢(谷)の方には下らない
・迷ってしまった仲間(同行者)を探す
ビバーク(野宿)するときには
・決断を早くしたら、場所の確保
不幸にして遭難してしまったら
・救難を待つ方法
雨、霧で視界不良のとき
・リーダーの判断と全員の協力
山の災害から身を守る
・怖い!がけ崩れ、土砂崩れ
「かみなり」が近づいてきたときの対処法
・かみなりの特徴をよく知る
熱中症に備える
・適度な塩分をとることが大切
ケガをしたときの止血法
・出血を見て止血をする
・止血法を選ぶ
ねんざ、打ち身、骨折などをしたとき
・ハイキングで多いのは「ねんざ」
ハチ、毒虫、毒ヘビなどにやられたとき
・応急処置を施したら、早めに病院へ
さる、クマの対策
・里山でも遭遇してしまうサルやクマ
人工呼吸と心肺蘇生法
・呼吸が止まっていたら人工呼吸
・心肺蘇生を行う
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。