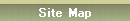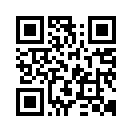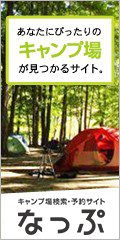『へたれ山ヤの漢気日記』 に訪問ありがとうございます。
『へたれ山ヤの漢気日記』 に訪問ありがとうございます。
 登山の道具,ウェア,グッズ,書籍,映像などのインプレと山行記録をメインに書いています。
登山の道具,ウェア,グッズ,書籍,映像などのインプレと山行記録をメインに書いています。 登山に関連するアウトドアやキャンプの道具&グッズ・書籍と幕営記録も書いています。
登山に関連するアウトドアやキャンプの道具&グッズ・書籍と幕営記録も書いています。 最近はマウンテンバイク『ROCKRIDER5.2』のポタリングやパーツレビューも書いています。
最近はマウンテンバイク『ROCKRIDER5.2』のポタリングやパーツレビューも書いています。 記事は全てカテゴリー別になっていますので宜しければ左サイドメニューの項目も参照下さい。
記事は全てカテゴリー別になっていますので宜しければ左サイドメニューの項目も参照下さい。 上部ナビボタンを使用すると当サイトの記事一覧や画像一覧等の検索が容易に出来ます。
上部ナビボタンを使用すると当サイトの記事一覧や画像一覧等の検索が容易に出来ます。 追記もしくは訂正の記述が特にない場合は記事投稿時点での価格及び情報になります。
追記もしくは訂正の記述が特にない場合は記事投稿時点での価格及び情報になります。 記事を参考に購入や加工等をされる場合は自己責任でお願いします(一切責任を負いません)
記事を参考に購入や加工等をされる場合は自己責任でお願いします(一切責任を負いません) 「IE」「Chrome」以外のブラウザ及びスマホ・携帯等では正常に表示されない場合があります。
「IE」「Chrome」以外のブラウザ及びスマホ・携帯等では正常に表示されない場合があります。 HOME >
SITE MAP >
参考書
>>
参考書№353 山でバテないテクニック
HOME >
SITE MAP >
参考書
>>
参考書№353 山でバテないテクニック記事投稿日:2013年11月13日
自身8冊目の「ヤマケイ山学選書」シリーズ。
登山においてバテとなる原因と対策をかわいいイラストと共に詳しく解説。
基本的事項に加えて効率的な行動食やサプリメントの摂取などもためになるが、気乗りのしない「つきあい山行」も精神面からのバテを誘発するという説が面白い。
自分がバテる原因でハッキリしているのは、
前夜出発⇒徹夜運転⇒駐車場に到着し少しでも仮眠を取ろうとするが、後からやって来る車のライトや音などで寝ることができず⇒結局寝不足のまま登山開始⇒早々に息切れのパターン。
これがほぼ100%の確率で起こるので、いかに少しでも仮眠ができるかが課題になっている。
ピークの17~20歳を過ぎれば誰でも落ちる体力。
それを補い楽しく登山できるノウハウの詰まった1冊。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【目次】
1:これが山でのバテだ
だれでもバテを経験する? 登山者100人のアンケート調査結果から
<ケース1>食べずに歩けばシャリバテは確実
<ケース2>体力の衰えを知らずしてバテる
<ケース3>筋肉痛もあなどれないバテのひとつ
<ケース4>ペース配分の失敗はバテのもとと知れ
<ケース5>酸素不足が原因する“高山病”というバテ
<ケース6>暑さでバテ、バテで凍死も・・・
<ケース7>体の不調は決定的なバテを招く
<ケース8>つき合い山行だとバテやすい?
<ケース9>楽しいはずが、睡眠不足でバテ山行に
<ケース10>低山なのに水筒を忘れてバテる
バテは体の危険信号。ならばバテないように歩く
2:体とバテのメカニズム
全身的なバテは、エネルギー源の不足に始まる
局所的なバテ=筋肉痛は、乳酸が引き起こす
体力ってなんだろう?
バテないための必要条件、全身持久力をつける
太っている人ほど要求される全身持久力
高山病になるかどうかは全身持久力次第
筋肉のメンテナンスにアミノ酸サプリメントを
筋持久力と筋力の違い。登山仕様の筋肉を鍛える
ストレスでバテないために、防衛体力が必要だ
どうすれば防衛体力が強化できるのだろうか
全身持久力トレーニングが防衛体力を高めるわけ
暑さ、寒さと体のしくみ。体温調節機能を高める
バテないために「今日も寝る」
やっかいな精神的ストレス克服法
男性より女性のほうがバテにくい?
年はとったがバテたくない。トレーニングで体力回復
3:山でバテないための栄養学
バテるかバテないかは日ごろの食事しだい
糖質、脂質、タンパク質で3000キロカロリーを
バテ防止のビタミン。不足はサプリメント・フーズで
汗で失う大切なミネラル。カルシウム不足は要注意
山行まで一ヶ月。バテない体を食事でつくる
早め早めの糖分摂取がバテないポイント
ランチタイムは1時間。食休みを必ずとる
山での食事は楽しく、おいしく。ならばバテない
「水で飲むとバテる」は迷信。少量ずつ分けて飲む
コーヒー、紅茶もバテ防止に効果を発揮
酒はバテ回復の妙薬、そしてバテの元凶
4:山でバテないためのトレーニング
トレーニングは日常生活からはじまっている
体をほぐすリラックス体操&ストレッチング
全身持久力を養うウォーキング&ジョギング
登山に要求される筋肉を鍛える筋力トレーニング
平衡感覚、敏捷性を養うためのトレーニング
プログラムの立て方とトレーニング実践法
山行一ヶ月前のトレーニングプログラム
5:山でバテないための25のテクニック
テクニック1 楽しみながら登ればバテない
テクニック2 単独行とパーティ山行、どちらがバテる?
テクニック3 体力の60パーセントで登れる山を選ぶ
テクニック4 情報収集はインターネットや関係機関から
テクニック5 標準コースタイムに50パーセントをプラス
テクニック6 バテのピーク“11時と15時”をクリアする
テクニック7 荷物は軽量かつコンパクトにまとめる
テクニック8 山行に合わせてザックを使い分けよう
テクニック9 レイヤードシステムで賢い着こなしを
テクニック10 登山靴は軽くてしっかりした構造のものを
テクニック11 疲れない交通機関の利用法
テクニック12 知っておきたいバテない歩行技術
テクニック13 出発前と歩き出しでバテを完封できる
テクニック14 岩稜、岩場ではスリルを楽しむつもりで
テクニック15 雪渓ではスプーンカットを利用する
テクニック16 丸木橋やゴーロでは途中で立ち止まらずに
テクニック17 休憩するよりペースを落として歩く
テクニック18 “新・三種の神器”でバテない山歩きを
テクニック19 暑い日は帽子とエリ付きシャツが有効
テクニック20 寒い時期はアンダーウェアに気を配ろう
テクニック21 雨具は高くてもしっかりしたものを
テクニック22 地図とコンパスで常に現在地の確認を
テクニック23 山小屋、テントで快適に過ごすためには
テクニック24 疲労回復の妙薬、ストレッチング&マッサージ
テクニック25 それでもバテてしまったときに
登山においてバテとなる原因と対策をかわいいイラストと共に詳しく解説。
基本的事項に加えて効率的な行動食やサプリメントの摂取などもためになるが、気乗りのしない「つきあい山行」も精神面からのバテを誘発するという説が面白い。
自分がバテる原因でハッキリしているのは、
前夜出発⇒徹夜運転⇒駐車場に到着し少しでも仮眠を取ろうとするが、後からやって来る車のライトや音などで寝ることができず⇒結局寝不足のまま登山開始⇒早々に息切れのパターン。
これがほぼ100%の確率で起こるので、いかに少しでも仮眠ができるかが課題になっている。
ピークの17~20歳を過ぎれば誰でも落ちる体力。
それを補い楽しく登山できるノウハウの詰まった1冊。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
楽天ブックスはこちら↓
|
【目次】
1:これが山でのバテだ
だれでもバテを経験する? 登山者100人のアンケート調査結果から
<ケース1>食べずに歩けばシャリバテは確実
<ケース2>体力の衰えを知らずしてバテる
<ケース3>筋肉痛もあなどれないバテのひとつ
<ケース4>ペース配分の失敗はバテのもとと知れ
<ケース5>酸素不足が原因する“高山病”というバテ
<ケース6>暑さでバテ、バテで凍死も・・・
<ケース7>体の不調は決定的なバテを招く
<ケース8>つき合い山行だとバテやすい?
<ケース9>楽しいはずが、睡眠不足でバテ山行に
<ケース10>低山なのに水筒を忘れてバテる
バテは体の危険信号。ならばバテないように歩く
2:体とバテのメカニズム
全身的なバテは、エネルギー源の不足に始まる
局所的なバテ=筋肉痛は、乳酸が引き起こす
体力ってなんだろう?
バテないための必要条件、全身持久力をつける
太っている人ほど要求される全身持久力
高山病になるかどうかは全身持久力次第
筋肉のメンテナンスにアミノ酸サプリメントを
筋持久力と筋力の違い。登山仕様の筋肉を鍛える
ストレスでバテないために、防衛体力が必要だ
どうすれば防衛体力が強化できるのだろうか
全身持久力トレーニングが防衛体力を高めるわけ
暑さ、寒さと体のしくみ。体温調節機能を高める
バテないために「今日も寝る」
やっかいな精神的ストレス克服法
男性より女性のほうがバテにくい?
年はとったがバテたくない。トレーニングで体力回復
3:山でバテないための栄養学
バテるかバテないかは日ごろの食事しだい
糖質、脂質、タンパク質で3000キロカロリーを
バテ防止のビタミン。不足はサプリメント・フーズで
汗で失う大切なミネラル。カルシウム不足は要注意
山行まで一ヶ月。バテない体を食事でつくる
早め早めの糖分摂取がバテないポイント
ランチタイムは1時間。食休みを必ずとる
山での食事は楽しく、おいしく。ならばバテない
「水で飲むとバテる」は迷信。少量ずつ分けて飲む
コーヒー、紅茶もバテ防止に効果を発揮
酒はバテ回復の妙薬、そしてバテの元凶
4:山でバテないためのトレーニング
トレーニングは日常生活からはじまっている
体をほぐすリラックス体操&ストレッチング
全身持久力を養うウォーキング&ジョギング
登山に要求される筋肉を鍛える筋力トレーニング
平衡感覚、敏捷性を養うためのトレーニング
プログラムの立て方とトレーニング実践法
山行一ヶ月前のトレーニングプログラム
5:山でバテないための25のテクニック
テクニック1 楽しみながら登ればバテない
テクニック2 単独行とパーティ山行、どちらがバテる?
テクニック3 体力の60パーセントで登れる山を選ぶ
テクニック4 情報収集はインターネットや関係機関から
テクニック5 標準コースタイムに50パーセントをプラス
テクニック6 バテのピーク“11時と15時”をクリアする
テクニック7 荷物は軽量かつコンパクトにまとめる
テクニック8 山行に合わせてザックを使い分けよう
テクニック9 レイヤードシステムで賢い着こなしを
テクニック10 登山靴は軽くてしっかりした構造のものを
テクニック11 疲れない交通機関の利用法
テクニック12 知っておきたいバテない歩行技術
テクニック13 出発前と歩き出しでバテを完封できる
テクニック14 岩稜、岩場ではスリルを楽しむつもりで
テクニック15 雪渓ではスプーンカットを利用する
テクニック16 丸木橋やゴーロでは途中で立ち止まらずに
テクニック17 休憩するよりペースを落として歩く
テクニック18 “新・三種の神器”でバテない山歩きを
テクニック19 暑い日は帽子とエリ付きシャツが有効
テクニック20 寒い時期はアンダーウェアに気を配ろう
テクニック21 雨具は高くてもしっかりしたものを
テクニック22 地図とコンパスで常に現在地の確認を
テクニック23 山小屋、テントで快適に過ごすためには
テクニック24 疲労回復の妙薬、ストレッチング&マッサージ
テクニック25 それでもバテてしまったときに
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。