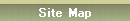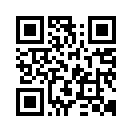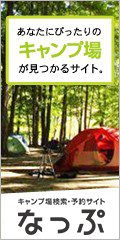『へたれ山ヤの漢気日記』 に訪問ありがとうございます。
『へたれ山ヤの漢気日記』 に訪問ありがとうございます。
 登山の道具,ウェア,グッズ,書籍,映像などのインプレと山行記録をメインに書いています。
登山の道具,ウェア,グッズ,書籍,映像などのインプレと山行記録をメインに書いています。 登山に関連するアウトドアやキャンプの道具&グッズ・書籍と幕営記録も書いています。
登山に関連するアウトドアやキャンプの道具&グッズ・書籍と幕営記録も書いています。 最近はマウンテンバイク『ROCKRIDER5.2』のポタリングやパーツレビューも書いています。
最近はマウンテンバイク『ROCKRIDER5.2』のポタリングやパーツレビューも書いています。 記事は全てカテゴリー別になっていますので宜しければ左サイドメニューの項目も参照下さい。
記事は全てカテゴリー別になっていますので宜しければ左サイドメニューの項目も参照下さい。 上部ナビボタンを使用すると当サイトの記事一覧や画像一覧等の検索が容易に出来ます。
上部ナビボタンを使用すると当サイトの記事一覧や画像一覧等の検索が容易に出来ます。 追記もしくは訂正の記述が特にない場合は記事投稿時点での価格及び情報になります。
追記もしくは訂正の記述が特にない場合は記事投稿時点での価格及び情報になります。 記事を参考に購入や加工等をされる場合は自己責任でお願いします(一切責任を負いません)
記事を参考に購入や加工等をされる場合は自己責任でお願いします(一切責任を負いません) 「IE」「Chrome」以外のブラウザ及びスマホ・携帯等では正常に表示されない場合があります。
「IE」「Chrome」以外のブラウザ及びスマホ・携帯等では正常に表示されない場合があります。 HOME >
SITE MAP >
参考書
>>
参考書№296 森の不思議 森のしくみ
HOME >
SITE MAP >
参考書
>>
参考書№296 森の不思議 森のしくみ記事投稿日:2013年01月12日
森の成り立ちや様々なトリビアを解説。
今まで読んだ森の参考書と違って学術的要素も違った角度から分かりやすく解説してあり、堅苦しさがなくとても読みやすいので頭に入りやすい。
植物の生き残るための知恵と進化には毎回感心させられる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【目次】
01 森と親しくなる第一歩
・寅さんのいる風景からわかること
・オオバコを見れば森がわかる?
・電車の窓から眺める森の姿
・山登りをしながら見る森の変化
・同じ場所で移り変わる植物を観察
02 「植物群落」と森のしくみ
・人間社会と似ている「植物群落」
・日本の森は高さの異なる4層構造
・森に生きる樹木の宿命
・武蔵野の雑木林が2層構造の理由
・樹木も競争・共存している
・森林の環境をまもる「マント群落」とは?
03 森林からみる日本列島の自然
・南から北へ代表的な森林3タイプ
・日本の森林のルーツは?
・高度による森の変化を見る
・太平洋側と日本海側の森の違い
・筑波山にみる南北斜面の違い
04 森の誕生から安定した森へ
・噴火のあとに森ができるまで
桜島の森にみる1000年の移り変わり
富士山麓・青木ヶ原樹海
草津白根山の針葉樹林
・山火事や伐採地からの出発
・武蔵野の雑木林を放置すると?
・都会が森になった姿を想像してみよう
05 植物たちの世代交代と寿命
・種子を散布するための工夫
・短命な種子と長寿の種子
・発芽のためのシステム
・森林内では静かに入れ替わりが進行
・長命な樹木と短命な樹木
06 森の植物を支配する温度・水・光
・光を上手に受けるための「樹形」
・生育に最適な温度と水環境
・寒さ対策は「落ち葉」と「冬芽の保護」
・樹木の水分を逃がさない工夫
・水分蒸散で体温調節
・極寒に耐える樹木と「凍裂」
・枝を伸ばして水を集める工夫
07 さまざまな生き残り戦術
・カタクリの「光の早採り作戦」
・自ら生活環境をつくるイタドリ
・濃い塩分に耐える海岸の植物
・海風に耐える海岸の低木植物
・雪の保温効果を利用するユキツバキ
・強風に耐えるオオシラビソの姿
・サバンナの植物、バオバブの貯水能
・厚い葉で乾燥に耐えるオリーブやコルクガシ
08 森と人とのかかわり
・日本には人工林が多い
・災害に弱いエリート集団の「人工林」
・雑木林の今後のあり方を考える
・全国で放置された竹林の弊害
・クズの繁茂が意味するもの
・「緑の島」に残された植物の問題
09 残したいブナ林・湿原・草原
・ブナ林の保護は、なぜ必要か?
・ブナ林は世界の基準植生
・ブナ林の減少と復元
・「自然保護」とは?
「自然保護」の5つの要素
「共通認識」をもち「自然保護」を進めたい
・湿原の保護
・草原の保護
10 公益性を生かす森の造成
・樹木に期待できる防火力
・関東大震災で生死を分けた2つの避難所
・東京都練馬区立大泉中学校での防火植林
・100年計画だった明治神宮の森
・大学キャンパスの参加型・緑化計画
・東京湾ゴミ埋立地に希望の「海の森」計画
今まで読んだ森の参考書と違って学術的要素も違った角度から分かりやすく解説してあり、堅苦しさがなくとても読みやすいので頭に入りやすい。
植物の生き残るための知恵と進化には毎回感心させられる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
楽天ブックスはこちら↓
|
【目次】
01 森と親しくなる第一歩
・寅さんのいる風景からわかること
・オオバコを見れば森がわかる?
・電車の窓から眺める森の姿
・山登りをしながら見る森の変化
・同じ場所で移り変わる植物を観察
02 「植物群落」と森のしくみ
・人間社会と似ている「植物群落」
・日本の森は高さの異なる4層構造
・森に生きる樹木の宿命
・武蔵野の雑木林が2層構造の理由
・樹木も競争・共存している
・森林の環境をまもる「マント群落」とは?
03 森林からみる日本列島の自然
・南から北へ代表的な森林3タイプ
・日本の森林のルーツは?
・高度による森の変化を見る
・太平洋側と日本海側の森の違い
・筑波山にみる南北斜面の違い
04 森の誕生から安定した森へ
・噴火のあとに森ができるまで
桜島の森にみる1000年の移り変わり
富士山麓・青木ヶ原樹海
草津白根山の針葉樹林
・山火事や伐採地からの出発
・武蔵野の雑木林を放置すると?
・都会が森になった姿を想像してみよう
05 植物たちの世代交代と寿命
・種子を散布するための工夫
・短命な種子と長寿の種子
・発芽のためのシステム
・森林内では静かに入れ替わりが進行
・長命な樹木と短命な樹木
06 森の植物を支配する温度・水・光
・光を上手に受けるための「樹形」
・生育に最適な温度と水環境
・寒さ対策は「落ち葉」と「冬芽の保護」
・樹木の水分を逃がさない工夫
・水分蒸散で体温調節
・極寒に耐える樹木と「凍裂」
・枝を伸ばして水を集める工夫
07 さまざまな生き残り戦術
・カタクリの「光の早採り作戦」
・自ら生活環境をつくるイタドリ
・濃い塩分に耐える海岸の植物
・海風に耐える海岸の低木植物
・雪の保温効果を利用するユキツバキ
・強風に耐えるオオシラビソの姿
・サバンナの植物、バオバブの貯水能
・厚い葉で乾燥に耐えるオリーブやコルクガシ
08 森と人とのかかわり
・日本には人工林が多い
・災害に弱いエリート集団の「人工林」
・雑木林の今後のあり方を考える
・全国で放置された竹林の弊害
・クズの繁茂が意味するもの
・「緑の島」に残された植物の問題
09 残したいブナ林・湿原・草原
・ブナ林の保護は、なぜ必要か?
・ブナ林は世界の基準植生
・ブナ林の減少と復元
・「自然保護」とは?
「自然保護」の5つの要素
「共通認識」をもち「自然保護」を進めたい
・湿原の保護
・草原の保護
10 公益性を生かす森の造成
・樹木に期待できる防火力
・関東大震災で生死を分けた2つの避難所
・東京都練馬区立大泉中学校での防火植林
・100年計画だった明治神宮の森
・大学キャンパスの参加型・緑化計画
・東京湾ゴミ埋立地に希望の「海の森」計画
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。