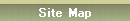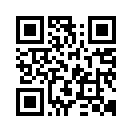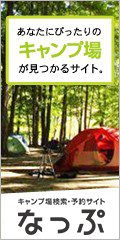『へたれ山ヤの漢気日記』 に訪問ありがとうございます。
『へたれ山ヤの漢気日記』 に訪問ありがとうございます。
 登山の道具,ウェア,グッズ,書籍,映像などのインプレと山行記録をメインに書いています。
登山の道具,ウェア,グッズ,書籍,映像などのインプレと山行記録をメインに書いています。 登山に関連するアウトドアやキャンプの道具&グッズ・書籍と幕営記録も書いています。
登山に関連するアウトドアやキャンプの道具&グッズ・書籍と幕営記録も書いています。 最近はマウンテンバイク『ROCKRIDER5.2』のポタリングやパーツレビューも書いています。
最近はマウンテンバイク『ROCKRIDER5.2』のポタリングやパーツレビューも書いています。 記事は全てカテゴリー別になっていますので宜しければ左サイドメニューの項目も参照下さい。
記事は全てカテゴリー別になっていますので宜しければ左サイドメニューの項目も参照下さい。 上部ナビボタンを使用すると当サイトの記事一覧や画像一覧等の検索が容易に出来ます。
上部ナビボタンを使用すると当サイトの記事一覧や画像一覧等の検索が容易に出来ます。 追記もしくは訂正の記述が特にない場合は記事投稿時点での価格及び情報になります。
追記もしくは訂正の記述が特にない場合は記事投稿時点での価格及び情報になります。 記事を参考に購入や加工等をされる場合は自己責任でお願いします(一切責任を負いません)
記事を参考に購入や加工等をされる場合は自己責任でお願いします(一切責任を負いません) 「IE」「Chrome」以外のブラウザ及びスマホ・携帯等では正常に表示されない場合があります。
「IE」「Chrome」以外のブラウザ及びスマホ・携帯等では正常に表示されない場合があります。 HOME >
SITE MAP >
参考書
>>
参考書№405 「体の力」が登山を変える
HOME >
SITE MAP >
参考書
>>
参考書№405 「体の力」が登山を変える記事投稿日:2015年02月18日
自身2冊目の「ヤマケイ新書」シリーズ。
登山運動を科学面から詳しく解説。
先日読んだ「山に登る前に読む本」と比べると文章が少々硬いので面白みに欠けるが、各項の色々なチャレンジテスト(検査)が参考になる。
自分的には特にアルコールに触れている章で「摂取後の車や自転車の運転には厳しいが、そもそも危険な行為をしている登山に対してはかなり許容されている」の内容を見て改めて考えさせられた。
山行(行動中)のアルコール摂取は運動能力や判断能力が低下し事故に繋がり易いのは明らか。
下界に照らし合わせれば飲酒運転と同じことになる。
科学的な面から登山を知りたい人にお勧めの1冊。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【目次】
はじめに-登山で見つける体の余裕
第1部 自分の体を知る
・登山で必要とする身体的機能
・登りの実力・下りの実力
・自分の予備能を知るために
・系統別臓器の実力とは
・「体の実力」を確かめるためのテストと注意事項
・生活習慣病対策としての「登山」
・パワーアップのための「山トレーニング」
・年代別「体」の変化
第2部 臓器のはたらきとパワーアップ
・活力の原動ポンプとエネルギーのパイプライン-循環器系(心臓・血管)
・心臓は体を動かすエンジン
・登りはつら!-登山で感じること
【数式に強い人のためのプラス情報:傾斜・移動速度と酸素消費の関係】
・心拍出漁の増やし方-更に詳しい科学情報
【数式に強い人のためのプラス情報:自覚的運動強度】
・心拍数を測るチャレンジテスト
【ランニングマシン】【MasterⅠ・Ⅱテスト】
・山でもスポーツ心臓-更なるパワーアップのために
・心拍数の定期的チェック-評価と継続的フォロー
・血管は、体のライフライン
・刻々と変化する血圧(血管の中の圧力)-登山で感じること
・血圧を変動させる因子-さらに詳しい科学情報
【数式に強い人のためのプラス情報:高血圧の正確な定義】
・血圧を測るチャレンジテスト
・酸素の少ない環境での血圧-更なるパワーアップのために
・血圧の下がり過ぎにも注意-評価と継続的フォロー
【ABI:ankle brachial index(太い動脈の詰まり具合を判定する検査】
【Allen test(手の血管の詰まり具合を判定する検査】
・大気から酸素を取り込む玄関口-呼吸器系(気道・肺)
・息が上がる、顎を出す-登山で感じること
・肺の中の酸素と二酸化炭素の関係-更に詳しい科学情報
【数式に強い人のためのプラス情報:呼吸で失われる水】
【数式に強い人のためのプラス情報:1日の体の水分の出入り】
・呼吸の調節能を知り呼吸機能を強化するチャレンジテスト
【息こらえ時間(呼吸をつかさどる中枢神経の検査】
【肺活量(最大使える呼吸の容量の検査】
【数式に強い人のためのプラス情報:肺活量の目安と肺年齢の計算法】
【呼気流速(空気の通り道-気管・気管支の検査】
【吹き上げパイプ(喘息や慢性気管支炎のなどのテスト】
・山の上での呼吸刺激-更なるパワーアップのために
・階段や坂を息を切らせずに登れるか-評価と継続的フォロー
・酸素を運ぶ宅配便-血液系(血液)
・登る前から、疲れやすい-登山で感じること
・ヘモグロビン量と酸素輸送能力-更に詳しい科学情報
【数式に強い人のためのプラス情報:血液の酸素含有量】
・血液を抜いた後での運動能力を知るチャレンジテスト
・登山と運動し過ぎの貧血対策-更なるパワーアップのために
・貧血対策-評価と継続的フォロー
・生体の化学工場であり清掃工場-代謝系(肝臓)
・肝臓の機能がもろに出るアルコール摂取-登山で感じること
・お酒に強い人、弱い人-更に詳しい科学情報
【数式に強い人のためのプラス情報:酒気帯び登山の規制濃度】
・飲酒後のバランス能力を知るチャレンジテスト
・下山後のお楽しみ?-評価と継続的フォロー
・動くための燃料供給装置-消化器系(胃腸)
・登山途中のエネルギー切れと摂取要求-登山で感じること
【数式に強い人のためのプラス情報:必要カロリーの計算法】
・エネルギーを発生させる化学反応と栄養吸収のコツ-更に詳しい科学情報
・無理矢理おなかをすかせるチャレンジテスト
・カーボローディング-更なるパワーアップのために
・頻繁な体重チェックで健康管理-評価と継続的フォロー
【コラム】生活習慣病予防のための体型チェック
・体の動き・働きを統合する司令塔―神経系(脳・脊髄・感覚器)
・平衡感覚に関わる脳・脊髄・眼
・薄暗くなると歩くのが怖い-登山で感じること
・平衡機能をつかさどる小脳と視覚による補正-更に詳しい科学情報
・バランス力と暗所視力を知るチャレンジテスト
・「バリアあり!」生活の勧め-評価と継続的フォロー
・総合機能に関わる脳
・ここがどこかわからない-登山で感じること
・認知機能低下の原因-更に詳しい科学情報
・病院でもやる認知機能チャレンジテスト
【ミニメンタルステート検査】【長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)】
・認知機能低下の防止法-評価と継続的フォロー
・皮膚感覚器も重要なファクター
・手足の感覚がない-登山で感じること
・凍傷の起こるメカニズム-更に詳しい科学情報
・冷却による知覚麻痺を体験するチャレンジテスト
【冷水負荷試験】
・動かすことで感覚を正常に維持-評価と継続的フォロー
・ 肉体の構造を維持する骨組みとスプリング-筋骨格系(筋肉と関節))
・距離を歩くと腰に痛み-登山で感じること
・筋肉痛・関節痛、そして関節傷害-更に詳しい科学情報
・関節傷害を早期発見するチャレンジテスト
膝のテスト:【マックマレーテスト】【アプレーの圧迫テスト】【前方引き出しテスト】【パトリックテスト】
脊髄のテスト:【下肢伸展挙上テスト(ラセーグテスト】【ブラガードテスト(Bragard sign)】
【大腿神経伸張テスト】
・忘れがちな側腹筋-更なるパワーアップのために
・関節を長持ちさせる工夫と腰痛体操-評価と継続的フォロー
【腰痛防止体操】腹筋を強化する体操/背筋を強化する体操
おわりに-自然を楽しみながら体を丈夫に保つために
登山運動を科学面から詳しく解説。
先日読んだ「山に登る前に読む本」と比べると文章が少々硬いので面白みに欠けるが、各項の色々なチャレンジテスト(検査)が参考になる。
自分的には特にアルコールに触れている章で「摂取後の車や自転車の運転には厳しいが、そもそも危険な行為をしている登山に対してはかなり許容されている」の内容を見て改めて考えさせられた。
山行(行動中)のアルコール摂取は運動能力や判断能力が低下し事故に繋がり易いのは明らか。
下界に照らし合わせれば飲酒運転と同じことになる。
科学的な面から登山を知りたい人にお勧めの1冊。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
楽天ブックスはこちら↓
|
【目次】
はじめに-登山で見つける体の余裕
第1部 自分の体を知る
・登山で必要とする身体的機能
・登りの実力・下りの実力
・自分の予備能を知るために
・系統別臓器の実力とは
・「体の実力」を確かめるためのテストと注意事項
・生活習慣病対策としての「登山」
・パワーアップのための「山トレーニング」
・年代別「体」の変化
第2部 臓器のはたらきとパワーアップ
・活力の原動ポンプとエネルギーのパイプライン-循環器系(心臓・血管)
・心臓は体を動かすエンジン
・登りはつら!-登山で感じること
【数式に強い人のためのプラス情報:傾斜・移動速度と酸素消費の関係】
・心拍出漁の増やし方-更に詳しい科学情報
【数式に強い人のためのプラス情報:自覚的運動強度】
・心拍数を測るチャレンジテスト
【ランニングマシン】【MasterⅠ・Ⅱテスト】
・山でもスポーツ心臓-更なるパワーアップのために
・心拍数の定期的チェック-評価と継続的フォロー
・血管は、体のライフライン
・刻々と変化する血圧(血管の中の圧力)-登山で感じること
・血圧を変動させる因子-さらに詳しい科学情報
【数式に強い人のためのプラス情報:高血圧の正確な定義】
・血圧を測るチャレンジテスト
・酸素の少ない環境での血圧-更なるパワーアップのために
・血圧の下がり過ぎにも注意-評価と継続的フォロー
【ABI:ankle brachial index(太い動脈の詰まり具合を判定する検査】
【Allen test(手の血管の詰まり具合を判定する検査】
・大気から酸素を取り込む玄関口-呼吸器系(気道・肺)
・息が上がる、顎を出す-登山で感じること
・肺の中の酸素と二酸化炭素の関係-更に詳しい科学情報
【数式に強い人のためのプラス情報:呼吸で失われる水】
【数式に強い人のためのプラス情報:1日の体の水分の出入り】
・呼吸の調節能を知り呼吸機能を強化するチャレンジテスト
【息こらえ時間(呼吸をつかさどる中枢神経の検査】
【肺活量(最大使える呼吸の容量の検査】
【数式に強い人のためのプラス情報:肺活量の目安と肺年齢の計算法】
【呼気流速(空気の通り道-気管・気管支の検査】
【吹き上げパイプ(喘息や慢性気管支炎のなどのテスト】
・山の上での呼吸刺激-更なるパワーアップのために
・階段や坂を息を切らせずに登れるか-評価と継続的フォロー
・酸素を運ぶ宅配便-血液系(血液)
・登る前から、疲れやすい-登山で感じること
・ヘモグロビン量と酸素輸送能力-更に詳しい科学情報
【数式に強い人のためのプラス情報:血液の酸素含有量】
・血液を抜いた後での運動能力を知るチャレンジテスト
・登山と運動し過ぎの貧血対策-更なるパワーアップのために
・貧血対策-評価と継続的フォロー
・生体の化学工場であり清掃工場-代謝系(肝臓)
・肝臓の機能がもろに出るアルコール摂取-登山で感じること
・お酒に強い人、弱い人-更に詳しい科学情報
【数式に強い人のためのプラス情報:酒気帯び登山の規制濃度】
・飲酒後のバランス能力を知るチャレンジテスト
・下山後のお楽しみ?-評価と継続的フォロー
・動くための燃料供給装置-消化器系(胃腸)
・登山途中のエネルギー切れと摂取要求-登山で感じること
【数式に強い人のためのプラス情報:必要カロリーの計算法】
・エネルギーを発生させる化学反応と栄養吸収のコツ-更に詳しい科学情報
・無理矢理おなかをすかせるチャレンジテスト
・カーボローディング-更なるパワーアップのために
・頻繁な体重チェックで健康管理-評価と継続的フォロー
【コラム】生活習慣病予防のための体型チェック
・体の動き・働きを統合する司令塔―神経系(脳・脊髄・感覚器)
・平衡感覚に関わる脳・脊髄・眼
・薄暗くなると歩くのが怖い-登山で感じること
・平衡機能をつかさどる小脳と視覚による補正-更に詳しい科学情報
・バランス力と暗所視力を知るチャレンジテスト
・「バリアあり!」生活の勧め-評価と継続的フォロー
・総合機能に関わる脳
・ここがどこかわからない-登山で感じること
・認知機能低下の原因-更に詳しい科学情報
・病院でもやる認知機能チャレンジテスト
【ミニメンタルステート検査】【長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)】
・認知機能低下の防止法-評価と継続的フォロー
・皮膚感覚器も重要なファクター
・手足の感覚がない-登山で感じること
・凍傷の起こるメカニズム-更に詳しい科学情報
・冷却による知覚麻痺を体験するチャレンジテスト
【冷水負荷試験】
・動かすことで感覚を正常に維持-評価と継続的フォロー
・ 肉体の構造を維持する骨組みとスプリング-筋骨格系(筋肉と関節))
・距離を歩くと腰に痛み-登山で感じること
・筋肉痛・関節痛、そして関節傷害-更に詳しい科学情報
・関節傷害を早期発見するチャレンジテスト
膝のテスト:【マックマレーテスト】【アプレーの圧迫テスト】【前方引き出しテスト】【パトリックテスト】
脊髄のテスト:【下肢伸展挙上テスト(ラセーグテスト】【ブラガードテスト(Bragard sign)】
【大腿神経伸張テスト】
・忘れがちな側腹筋-更なるパワーアップのために
・関節を長持ちさせる工夫と腰痛体操-評価と継続的フォロー
【腰痛防止体操】腹筋を強化する体操/背筋を強化する体操
おわりに-自然を楽しみながら体を丈夫に保つために
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。